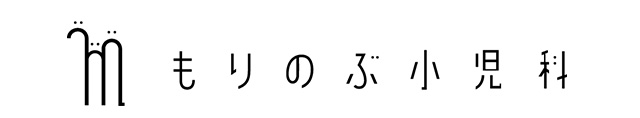2023/12/26
小児肺炎球菌感染症について
子どもが日常的に感染する病気の一つである、肺炎球菌感染症についてご存知でしょうか。
肺炎球菌は5歳未満の小児が感染すると、日常的な感染症から細菌性髄膜炎等の重篤な感染症を起こすことがあるため、予防接種が重要です。
本記事では小児の肺炎球菌感染症について、以下の点を中心に解説します。
- 小児の肺炎球菌感染症とは
- 肺炎球菌感染症の症状
- 小児の肺炎球菌感染症の予防方法
- 肺炎球菌ワクチンは高齢者でも定期接種がある
小児の肺炎球菌感染症について適切に理解し、重症化しないようにするために、そして感染対策を行うための参考にしていただければ幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
小児の肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌は細菌感染症のひとつで、発症すると肺炎や中耳炎、菌血症、細菌性髄膜炎を起こす可能性があります。
細菌性髄膜炎は0から3歳を中心に5歳未満で発症することが多く、肺炎球菌による菌血症・敗血症が起きる重篤な状態に陥ることもあるため注意が必要な病気です。
ここからは肺炎球菌の特徴や感染の仕方をご紹介します。
子どもの鼻やのどにいる
肺炎球菌は鼻や喉の奥に常在している身近な菌です。
成人にも常在していますが、乳幼児の鼻やのどに常在している割合が高いです。
健康な状態であれば肺炎球菌を保菌していても問題はないですが、発症すると、重篤な細菌性髄膜炎の他に、細菌性肺炎や急性中耳炎などの日常的な疾患の原因にもなります。
乳児で細菌性髄膜炎などの重篤な病気を起こすことがある
小児が肺炎球菌に感染し重篤な場合は、初期症状は発熱だけで感染巣が明確でない菌血症を発症している症例があります。
また、肺炎球菌による細菌性髄膜炎は菌血症を介して発症することや、直接発症することがあります。
また、人工内耳の医療器具を装着している小児は中耳炎に続いて発症するリスクがあります。
日本で肺炎球菌ワクチンが導入される前の時代、特に細菌性髄膜炎が発症した場合2%の子どもが亡くなるリスクがあると報告されており、生存した子どもの10%には難聴や精神発達遅滞、四肢の麻痺、てんかんなどの後遺症が残ると言われています。
幼い子どもほど発症しやすく、特に0歳児のリスクが高いです。
肺炎球菌の感染の仕方
肺炎球菌は咳やくしゃみなどの飛沫による感染が多いです。
予防接種前の健康な1歳児の肺炎球菌の保菌率は30%〜50%ですが、保育園や幼稚園での集団生活が始まって1〜2ヶ月ほどで保菌率は80%以上になると言われています。
0〜1歳に受ける定期予防接種の肺炎球菌ワクチンを接種して、免疫を持つことが大切です。
肺炎球菌感染症の症状
肺炎球菌は感染した部位によって症状が異なり、中耳炎、肺炎、菌血症、細菌性髄膜炎などがあります。
以下で、それぞれの症状をご紹介します。
中耳炎
以前は肺炎球菌が原因の小児の急性中耳炎の報告が多かったです。
中耳炎の症状は、急性外耳炎に起因しない耳漏の出現、耳痛、鼓膜の膨隆や発赤などがあります。
しかし症状を自分で伝えられない小児の場合は、耳を押さえたり、引っ張る、機嫌が悪い、こすりつける、といった行動を起こすことが報告されています。
そのため、耳をよく触るようになったり、耳をss触られるのを嫌がったり、泣き止まないなど普段と違う様子がありましたら、病院の受診を検討してください。
肺炎
肺炎球菌による肺炎は、小児の細菌性肺炎の最も多い原因とされています。
肺炎を発症すると、ひどい咳、持続する発熱、呼吸苦があり、酸素飽和度が低下します。
乳児が肺炎を発症して病状が重症化すると、食事や水分摂取が難しくなり、睡眠障害を認め、入院加療が必要になる事が多いです。
肺炎は、世界の中でも小児の主要な死因のひとつとされているため注意が必要です。
菌血症
本来は無菌である血液に、肺炎球菌などの菌が感染した状態を菌血症といいます。
主な症状は発熱で、診断は血液培養検査や尿検査、尿培養検査で行います。
菌血症が重症化して敗血症になると、組織障害や臓器障害を引き起こし命の危険が伴います。
小児、特に乳児が侵襲性の高い肺炎球菌に感染すると重症な経過を取りやすく、菌血症を発症する確率が高いです。
次に述べる細菌性髄膜炎との合併もあります。
細菌性髄膜炎
何らかのきっかけで、脳脊髄膜に菌が入り込むと発症する細菌性髄膜炎は、肺炎球菌が原因の場合は致死率が特に高く後遺症が残りやすい傾向にあります。
肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンが定期接種に追加される前は、日常的に細菌性髄膜炎が見られました。
重篤な状態で、発熱や頭痛、嘔吐などの症状があり、意識障害や痙攣重積が起こります。
乳幼児の場合は、発熱以外に食欲低下や不機嫌、顔色不良になるなど症状が分かりにくいため発見が遅れてしまう危険があります。
定期接種が開始される前は、0歳から2歳の乳幼児が細菌性髄膜炎に罹患する子が多かったです。
小児の肺炎球菌感染症の予防方法
小児の肺炎球菌感染症の予防方法をご紹介します。
小児用肺炎球菌ワクチン
1990年代の世界全体での肺炎球菌感染症が原因の小児の死亡数は、年間で100〜200万人とされています。
日本でも5歳未満の小児が肺炎球菌が原因で髄膜炎を発症する確率が高かったのですが、2012年に肺炎球菌のワクチンが普及して以降、発症件数が減少しました。
最初に普及したワクチンは「沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン」です。
90以上の種類がある肺炎球菌の中で、特に重篤な症状を引き起こす可能性の高い、7種類の肺炎球菌の成分に予防が期待できるワクチンです。
その後、2013年6月に新しく承認された「沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン」に変更され、さらに6種類の成分の予防が期待できるようになりました。
肺炎球菌は、抗菌薬による治療が発達した近年でも重篤な後遺症を残したり、命の危険が伴う重症細菌感染症(細菌性髄膜炎など)を引き起こす可能性が高い細菌です。
そのため、ワクチンでの予防が非常に重要になります。
ワクチンは生後2ヶ月から可能
小児用肺炎球菌ワクチンは生後2ヵ月から接種が可能です。
標準的には、肺炎球菌ワクチンは4回ワクチンを接種します。
しかし、生後7ヵ月以上経ってから開始すると接種できる回数が減ってしまいます。
2歳未満の乳幼児が重症化する肺炎球菌による細菌性髄膜炎のリスクが高いので、生後2ヵ月以上経ったらワクチン接種を開始することをおすすめします。
ワクチン接種スケジュール
小児用肺炎球菌ワクチンはワクチン接種を開始した月齢によって接種できる回数が変わります。
以下の表にまとめたので参考にしてください。(厚生労働省)
| 接種開始年齢 | 初回接種 | 追加接種 |
|---|---|---|
| 生後2か月以上 7か月未満 | 27日以上の間隔をおいて 1歳までに3回接種 | 1歳~1歳3ヶ月の間に初回接種終了後 60日以上の間隔をおいて1回 |
| 生後7か月以上 1歳未満 | 27日以上の間隔をおいて 1歳までに2回接種 | 1歳以降に初回接種終了後 60日以上の間隔をおいて1回 |
| 1歳以上2歳未満 | 1回接種 | 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回 |
| 2歳以上5歳未満 | 1回接種 | なし |
肺炎球菌ワクチンは高齢者も定期接種がある
肺炎球菌ワクチンには、13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)、15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)、23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)があります。
成人の肺炎球菌感染症は50歳台以上で発症する確率が高く、小児とは異なり重症の肺炎が多いのが特徴です。
また、死亡例や後遺症が残るケースがあります。
そのため、2014年10月1日からは高齢者を対象にした肺炎球菌ワクチンの定期接種が開始されています。
成人で使用する肺炎球菌ワクチンは、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回接種します。
健康な人では、少なくとも接種後5年間は効果が持続するとされています。
また、肺炎は様々な原因で引き起こる疾患であり、肺炎球菌には多くの異なる血清型が存在します。
そのため、過去に肺炎や肺炎球菌感染症にかかったことがある場合でも、定期接種の対象となります。
その他に、23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)の対象者は、
2歳以上で脾臓摘出患者における肺炎球菌による感染症の発症予防(健康保険適用あり)、鎌状赤血球などの脾機能不全のある患者、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、糖尿病等の基礎疾患のある患者、免疫抑制作用のある治療を予定されている者で、治療開始まで2週間以上の余裕のある患者となります。
まとめ
ここまで小児の肺炎球菌感染症についてお伝えしてきました。
小児の肺炎球菌感染症の要点をまとめると以下の通りです。
- 肺炎球菌は子どもの鼻やのどにいる常在菌で保菌しているだけでは発症しない
- 肺炎球菌ワクチンが定期接種に導入される前、重篤な感染症である細菌性髄膜炎は2歳未満の乳幼児が多く罹患していた
- 小児の肺炎球菌感染症の予防にはワクチンを定期接種する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
- 厚生労働省 ”肺炎球菌感染症(小児)”
- NIID 国立感染症研究所 ”IASR” Vol. 44 肺炎球菌感染症
- 厚生労働省 ”小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A”
- 厚生労働省.”肺炎球菌コンジュゲートワクチン(小児用)Q&A <医療従事者用>”
- 厚生労働省 ”肺炎球菌感染症(高齢者)”
- 厚生労働省 ”侵襲性肺炎球菌感染症 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について”
- 厚生労働科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「保育所等における感染症対策に関する研究」平成28年度研究報告書
- 小児急性中耳炎 診療ガイドライン2018年度版
- 厚生労働省検疫所.”肺炎について(ファクトシート)
- 東京都感染症情報センター ”侵襲性肺炎球菌感染症 Invasive pneumoniae disease”
- 日本化学療法学会雑誌第59巻第6号 ”IPD の実態とその予防としての肺炎球菌ワクチン「わが国における侵襲性肺炎球菌感染症の実態とその予防としての肺炎球菌ワクチン」”
- NIID 国立感染症研究所 ”細菌性髄膜炎とは “
- NIID 国立感染症研究所 ”今後期待される新規肺炎球菌ワクチン”
- 2023 予防接種に関するQ&A集 一般社団法人 日本ワクチン産業協会 参照100-121ページ