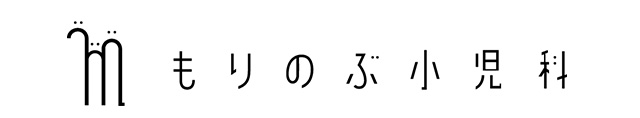2026/01/19
狂犬病について
狂犬病は、動物から人に感染する病気として知られていますが、日本では長年発生が確認されていないことから、身近な感染症として意識する機会は多くありません。
しかし、海外では現在も発生が続いており、動物との接触を通じて感染する可能性がある病気です。
本記事では狂犬病について、以下の点を中心に解説します。
- 狂犬病とはどのような感染症か
- 狂犬病の症状と特徴
- 狂犬病の予防方法
狂犬病について正しく理解し、万が一の場面に備えるための参考にしていただければ幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
狂犬病とは?
狂犬病は、狂犬病ウイルスによって引き起こされる感染症で、人と動物の双方に感染する人獣共通感染症です。
主に動物から人へ感染し、中枢神経系に障害を起こすことが知られています。
発症した場合には重い経過をたどることが多いため、世界的に見ても重要な感染症の一つとされています。
日本では長年、人の狂犬病の発生は確認されていませんが、海外では現在も多くの国で報告が続いています。
そのため、国内では身近に感じにくい病気であっても、海外渡航時や動物との接触を通じて感染する可能性がある感染症として注意が必要とされています。
狂犬病の原因と感染経路
狂犬病の原因は、狂犬病ウイルスに感染することです。
このウイルスは、感染している動物の唾液に含まれており、多くの場合、動物に咬まれることがきっかけで人に感染します。
感染源として多いのは犬ですが、キツネ、アライグマ、コウモリなども感染源になることがあります。
地域によって感染源となる動物の種類には違いがありますが、多くの国で犬を介した感染が問題になっています。
ウイルスは、咬まれた傷口や皮膚の小さな傷、目や口などの粘膜から体内に入ります。
人から人へ感染することは、極めてまれとされています。
体内に侵入したウイルスは、傷口付近の神経に入り、神経を伝って少しずつ脳へ向かって進んでいきます。
症状が現れるまでの期間には個人差があり、咬まれた場所や傷の深さ、体内に入ったウイルスの量などによって変わるといわれています。
狂犬病の症状
狂犬病の症状は、感染してからすぐに現れるわけではなく、一定の潜伏期間を経てから出現します。
潜伏期間には個人差があり、多くは1ヶ月から3ヶ月ですが、1週間や1年を経て発症することがあります。
初期にはかぜのような症状に似ているため、狂犬病と気づかれにくいことがありますが、進行するにつれて神経に関わる症状が現れることが特徴です。
初期症状
狂犬病の初期には、発熱、頭痛、全身のだるさなど、かぜに似た症状が見られることがあります。
この段階では、体調不良として見過ごされてしまうことも少なくありません。
また、咬まれた部位の周囲に、痛みやチクチクする感じ、焼けるような違和感が現れることがあります。
これらは、ウイルスが神経に影響を及ぼし始めた際にみられる可能性がある症状とされています。
進行した場合に見られる症状
症状が進行すると、神経の働きに関わる異常が目立つようになります。
不安感や強い緊張、興奮がみられ、言動が落ち着かなくなったり、幻覚を見たり、錯乱したりといった精神症状が出る場合があります。
意識がはっきりしない時間帯が出ることもあります。
さらに進むと、飲み込む動きに合わせてのどの筋肉がけいれんし、水を前にすると強い恐怖や苦痛を感じて飲めなくなる状態(恐水症)が現れることがあります。
風が当たる刺激を嫌がるようになるケースも知られています。
重い段階では、全身のけいれんや麻痺、意識の低下が進み、最終的には呼吸の働きが弱くなって生命が保てなくなる経過をたどるとされています。
狂犬病の治療方法
狂犬病は、発症してからの治療が難しい感染症とされています。
現在の医療では、発症後にウイルスそのものを排除する確実な治療方法は確立されていません。
動物に咬まれた場合には、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。
応急処置としては、傷口を流水と石けんで十分に洗い流し、体内に入るウイルスの量を減らすことが勧められています。
医師が感染の可能性があると判断した場合には、狂犬病ワクチンの接種が行われます。
必要に応じて、免疫グロブリンが併用されることもあります。
国内で対応できる医療機関は渡航外来等の専門外来で相談できる可能性があります。
すでに狂犬病を発症している場合には、症状をやわらげる治療が中心となりますが、現時点では根本的な治療法はないとされています。
狂犬病はどの地域で発生しているか
狂犬病は、日本ではほとんど見られない感染症ですが、世界的には現在も多くの国で発生が続いています。
地域によって発生状況には大きな差があり、国や地域ごとの事情を知っておくことが大切です。
日本における発生状況
日本では、1950年の狂犬病予防法制定後、1956年の報告を最後に、長年にわたり国内での狂犬病の発生は確認されていません。
海外で感染し、国内で発症したケースが、1970年、2006年、2020年に報告され、いずれも成人で死亡されています。
現在は、国内での感染リスクはきわめて低い状態が維持されています。
また、犬を対象とした狂犬病予防対策が法律によって定められており、犬の登録や定期的なワクチン接種が実施されています。
野良犬を見かけることのない、珍しい国です。
これにより、国内での狂犬病の侵入や拡大を防ぐ体制が整えられています。
ただし、海外から動物が持ち込まれるケースもあるため、水際での検疫体制が重要とされています。
日本では、輸入動物に対して検疫が行われ、感染の疑いがある動物が国内に入らないよう管理が続けられています。
海外における発生状況
海外では、現在も多くの国で狂犬病が流行しており、特にアジアやアフリカの一部地域では、日常的に発生が報告されています。
中国では、2021年には157人が発症しています。
これらの地域では、犬を介した感染が主な原因とされています。
海外では、医療体制やワクチン接種の普及状況に地域差があるため、狂犬病の制圧が難しい場所もあります。
その影響で、毎年多くの人が感染し、命を落としている地域があることが公表されています。
海外渡航の際には、現地での動物との接触に注意することが求められています。
特に、野良犬や野生動物に近づかないことが重要です。
イヌ、ネコ、コウモリ等の野生哺乳動物に引っ掛かれたり、噛まれたりした際には、傷口を石鹸と流水で洗い流して、速やかに医療機関を受診してください。
あらかじめ狂犬病ワクチンを接種しても、暴露後免疫のためのワクチン接種が必要です。
狂犬病の予防
狂犬病は、発症すると治療が難しい感染症であるため、予防が最も重要とされています。
日常生活の中での心がけと、動物との接し方が感染を防ぐポイントになります。
また、狂犬病ワクチンが日本でも認可されて、接種が可能です。
不活化狂犬病ワクチン
狂犬病常在地域への渡航前の予防接種や、狂犬病ウイルスを保有する動物に接種後の発症予防(暴露後免疫)にも使用できます。
動物用のワクチンとは、異なる製剤です。
予防接種スケジュール
狂犬病の予防
3回接種(接種0日目、7日目、21日目)又は(接種0日目、7日目、28日目) 1.0mlを筋肉内に接種。
接種対象年齢は、小児では特に制限はなく、1歳未満でも接種可能ですが、1歳までは両親に抱っこされているので、イヌ等に近づくことはないと思われます。
イヌ等の動物に近づけるようになる2-3歳からは、渡航前に接種を検討した方が良いと考えます。
狂犬病の発病予防(暴露後接種)
狂犬病発症動物や、その疑いのある動物と接触した場合、4回から6回筋肉内に接種。
2018年のWHOの推奨接種スケジュールでは、暴露前接種が完了している人は、2回接種という方法もあります。
まず、動物にむやみに触れないことが大切です。
特に野犬や野良猫、野生動物との接触は避けるようにしましょう。
海外では狂犬病が発生している地域も多いため、旅行中に動物に近づいたり、えさを与えたりしないよう注意が必要です。
ペットを飼っている家庭では、犬に狂犬病ワクチン(動物用)の接種を受けさせることが重要とされています。
定期的なワクチン接種により、犬が感染することを防ぎ、人への感染リスクを下げる効果が期待されています。
万が一、動物に咬まれた場合には、すぐに傷口を流水と石けんでよく洗い流し、医療機関を受診してください。
見た目に軽い傷であっても、放置せず医師に相談することが勧められています。
狂犬病は、正しい対応と予防行動によって感染を防ぐことができる病気です。
日頃から動物との接し方に気を配り、必要な予防対策を行うことが大切です。
まとめ
ここまで、狂犬病についてお伝えしてきました。
狂犬病の要点をまとめると以下の通りです。
- 狂犬病は動物から人に感染する人獣共通感染症で、中枢神経に重い障害を起こすことのある病気
- 初期はかぜに似た症状でも、時間をかけて進行すると神経症状が現れ、重篤な経過をたどることがある点が特徴
- 日本では発生していないものの、海外では流行しており、狂犬病の発生地に渡航する場合は、狂犬病予防で暴露前免疫のために渡久地に接種を受けることや、動物との接触回避などの予防行動が重要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
- 世界保健機関(WHO). “Rabies”. 2024-06-05.
- 厚生労働省. “狂犬病”.
- 厚生労働省. “狂犬病(Rabies)”. 2024-03.
- NIID 国立感染症研究所. “狂犬病”.2025-06-26.
- さいたま市. “狂犬病”. 2025-06-10.
- 大分大学医学部. “狂犬病、狂犬病ワクチンについて”
- 予防接種に関するQ&A集 一般社団法人日本ワクチン産業協会 2025年 岡部信彦、多屋馨子